西村 明
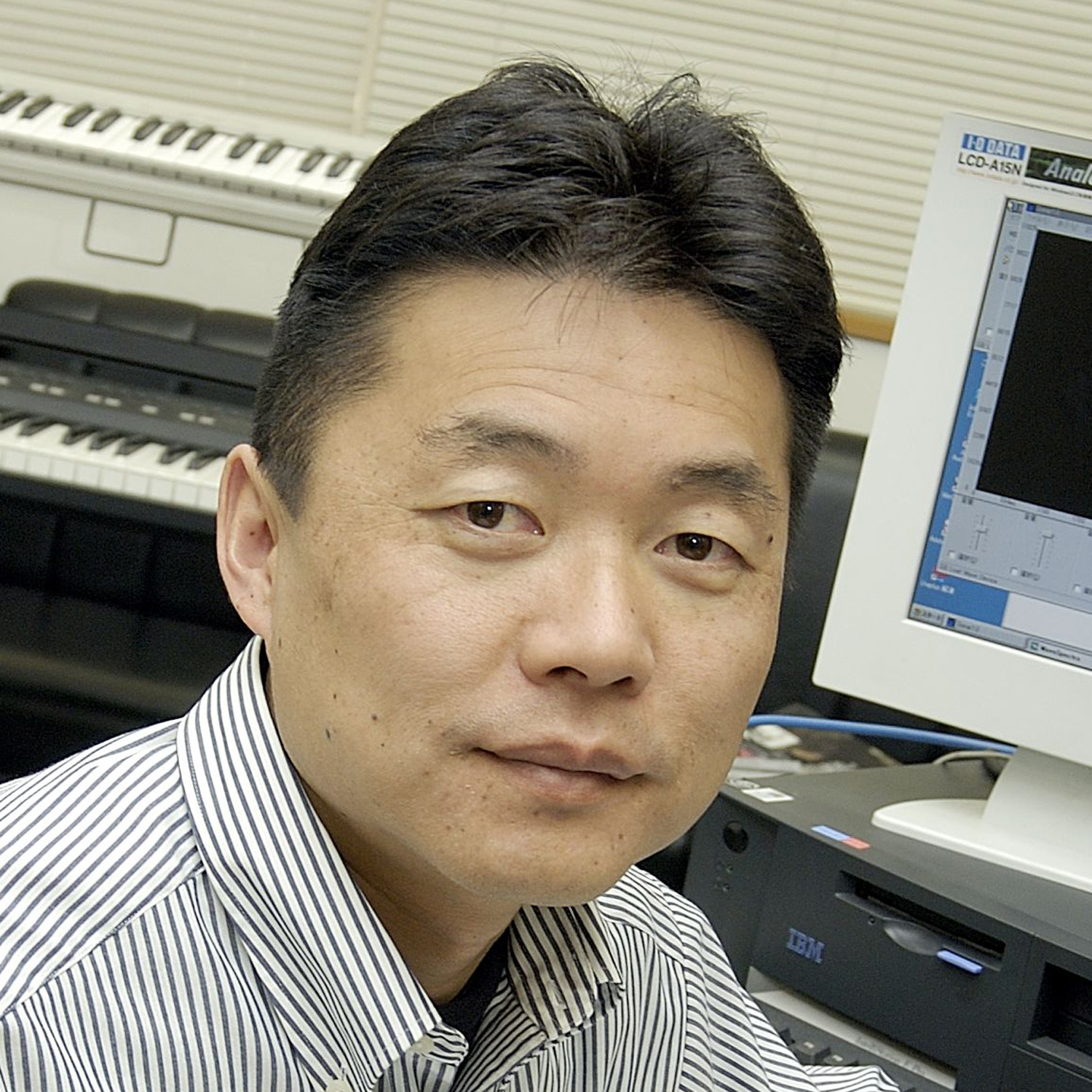
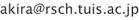
| 所属 | 情報メディア学系/メディアデザイン研究室 | 職名 | 教授 |
| 研究テーマ | 音響メディアと人間の知覚/認知/感性情報処理に関する研究 | ||
メッセージ
大学に入るまでは、既に答えが分かっているものばかり勉強してきたはずですが、大学では、自ら問題を見つけ解決する方法を学んでいってもらいたいと思います。
大切にしているものは?
月並みですが、家族です。
研究内容
音を記録/保存/伝送/再生する技術が生まれて約130年、21世紀の現代では、CDやMD、携帯電話といったディジタル信号処理技術を活用した音響メディアが、我々の生活を豊かにしているといえます。近年の新しい音響メディアは、CDより記録/伝送される情報量が多い高品質なメディア(DVD Audio、Super AudioCD、マルチチャンネルオーディオ)と、限られた記録/伝送情報量でベストな品質を目指すメディア(MP3、MDなどの音響情報圧縮メディア、携帯電話など)の2極化が進んでいるようです。
これら新しい音響メディアを使うのはあくまで人間ですから、メディアが記録し再生する音を、人間がどう捉え、どのように感じとっているか、つまり人間の内部で行われる音情報処理の仕組みがどうなっているか、を調べておくことが重要であると言えます。例えば、前者の高品質メディアの場合、DVD Audio や Super Audio CDが記録できる超音波は、人間の聴こえにどう影響しているか、といった問題や、従来の2チャンネルオーディオより空間的な表現能力が高まった5.1チャンネルオーディオの効果的な利用方法を追求するには、人間が音の方向や広がり感をどのように知覚しているのかという問題があります。後者の音情報圧縮メディアでは、人間にとって聞こえにくい音の情報を取り去ることによって、情報量低減と高音質の両立を目指していますが、どのような状況でどのような音が人間にとって聞こえにくいのかを調べることは、さらなる圧縮率の向上に繋がる基礎的な研究となります。このような、新しい音響メディアに対応する、人間の聴こえの様子を調べることが、研究テーマとなっています。
新しい音響メディアに限らず、現在広く使われているCDメディアにも、音質を左右する要因があることが、オーディオマニアの間では定説になっています。しかし、どのような要因がどれだけ音質に影響するのか、といった科学的な分析はほとんど行われていないのが現状であり、新たな性能測定方法の開発や音質評価といった研究も、テーマのひとつです。さらに、古いメディアであるLPレコードやカセットテープに記録されている音の音質劣化を自然に補正する技術を開発し、市販のソフトウェアに採り入れられるという成果を挙げることができました。
また、楽器も広い意味では、音楽を再現する音響メディアであると言えます。"良い音"のする楽器の音は、そうでない楽器の音とどこが違うのでしょう?どういう音が"良い楽器の音"なのでしょう?このことを明らかにするには、楽器音の特徴を分析し、良い悪いといった音に対する人間の評価との関係を調べる必要があります。そのような研究は古くから行われていましたが、近年のコンピュータの急速な発達によって、より精密な分析と楽器音の合成が可能になったことを利用して、新たな"楽器音らしさ"に繋がる音の特徴を見つける研究も行っています。
これら新しい音響メディアを使うのはあくまで人間ですから、メディアが記録し再生する音を、人間がどう捉え、どのように感じとっているか、つまり人間の内部で行われる音情報処理の仕組みがどうなっているか、を調べておくことが重要であると言えます。例えば、前者の高品質メディアの場合、DVD Audio や Super Audio CDが記録できる超音波は、人間の聴こえにどう影響しているか、といった問題や、従来の2チャンネルオーディオより空間的な表現能力が高まった5.1チャンネルオーディオの効果的な利用方法を追求するには、人間が音の方向や広がり感をどのように知覚しているのかという問題があります。後者の音情報圧縮メディアでは、人間にとって聞こえにくい音の情報を取り去ることによって、情報量低減と高音質の両立を目指していますが、どのような状況でどのような音が人間にとって聞こえにくいのかを調べることは、さらなる圧縮率の向上に繋がる基礎的な研究となります。このような、新しい音響メディアに対応する、人間の聴こえの様子を調べることが、研究テーマとなっています。
新しい音響メディアに限らず、現在広く使われているCDメディアにも、音質を左右する要因があることが、オーディオマニアの間では定説になっています。しかし、どのような要因がどれだけ音質に影響するのか、といった科学的な分析はほとんど行われていないのが現状であり、新たな性能測定方法の開発や音質評価といった研究も、テーマのひとつです。さらに、古いメディアであるLPレコードやカセットテープに記録されている音の音質劣化を自然に補正する技術を開発し、市販のソフトウェアに採り入れられるという成果を挙げることができました。
また、楽器も広い意味では、音楽を再現する音響メディアであると言えます。"良い音"のする楽器の音は、そうでない楽器の音とどこが違うのでしょう?どういう音が"良い楽器の音"なのでしょう?このことを明らかにするには、楽器音の特徴を分析し、良い悪いといった音に対する人間の評価との関係を調べる必要があります。そのような研究は古くから行われていましたが、近年のコンピュータの急速な発達によって、より精密な分析と楽器音の合成が可能になったことを利用して、新たな"楽器音らしさ"に繋がる音の特徴を見つける研究も行っています。
発表・著書等
論文・著書など
「TCP/IPネットワークとWWWブラウザを用いる聴覚訓練システム」
日本音響学会誌. Vol.62,no.3(2006) pp.208-213
「振幅変調を用いた音響信号への電子透かしデータの埋め込み・検出装置」
特許願 2005-71245(2005)
Akira Nishimura, Nobuo Koizumi, "Measurement and analysis of sampling jitter in digital audio products"
Proceedings of the 18th International Congress on Acoustics, IV. 2004, pp.2547-2550
"An auditory model that can account for frequency selectivity and phase effects on masking"
Acoustical Science and Technolory, Vol.25,no.5 (2004), pp.330-339
西村明,小泉宣夫,「ディジタル・オーティオ機器におけるサンプリング・ジッターの諸様相とその要因」 東京情報大学研究論集, Vol.7,no.2(2004), pp.79-92
日本音響学会誌. Vol.62,no.3(2006) pp.208-213
「振幅変調を用いた音響信号への電子透かしデータの埋め込み・検出装置」
特許願 2005-71245(2005)
Akira Nishimura, Nobuo Koizumi, "Measurement and analysis of sampling jitter in digital audio products"
Proceedings of the 18th International Congress on Acoustics, IV. 2004, pp.2547-2550
"An auditory model that can account for frequency selectivity and phase effects on masking"
Acoustical Science and Technolory, Vol.25,no.5 (2004), pp.330-339
西村明,小泉宣夫,「ディジタル・オーティオ機器におけるサンプリング・ジッターの諸様相とその要因」 東京情報大学研究論集, Vol.7,no.2(2004), pp.79-92
学位・研究業績等
researchmap(外部リンク)
